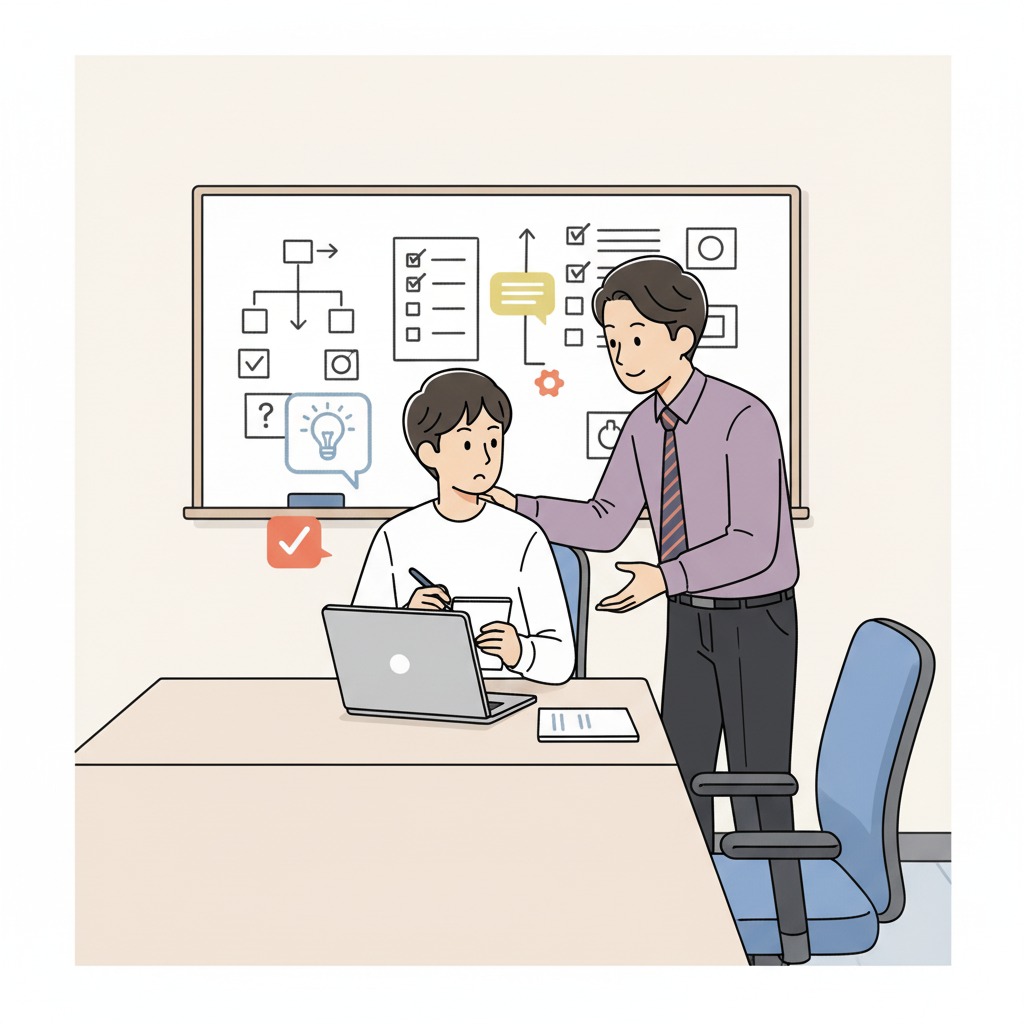
あらすじ
ユウタは入社2年目の若手エンジニア。最近、コードレビューで毎回細かい指摘を受けることが多く、自分のコードに自信が持てずにいた。
「提出しても、どうせ指摘されるんだ…」という気持ちが先に立ち、コードを書くモチベーションにも影響が出始めている。
そんなユウタに先輩が声をかける。「レビューは単なる突っ込みを受ける場じゃなく、自分のコードの品質を高める場だよ」と。
先輩は、ユウタが自信を持ってコードを提出できるように、事前チェックの習慣として 3つの具体的なメソッド を伝授することにした。
ユウタ
「先輩、今回もレビューで指摘がいっぱい来るんじゃないかと思うと、提出する前から不安です…。毎回同じようなミスをしてしまって、正直どうしたらいいのかわかりません。」
先輩
「ユウタ、それはよくある悩みだね。でも、レビューは突っ込みを待つ場じゃなく、自分のコードをさらに良くするための場だと思えば、取り組み方が変わるよ。」
ユウタ
「確かに…。でも、具体的にどうやって自分でチェックすればいいんでしょうか?」
先輩
「まずは、提出前にできる事前チェックの習慣をつけること。今日は3つのメソッドを紹介するから、一緒にやってみよう。」
① リスクポイント抽出法
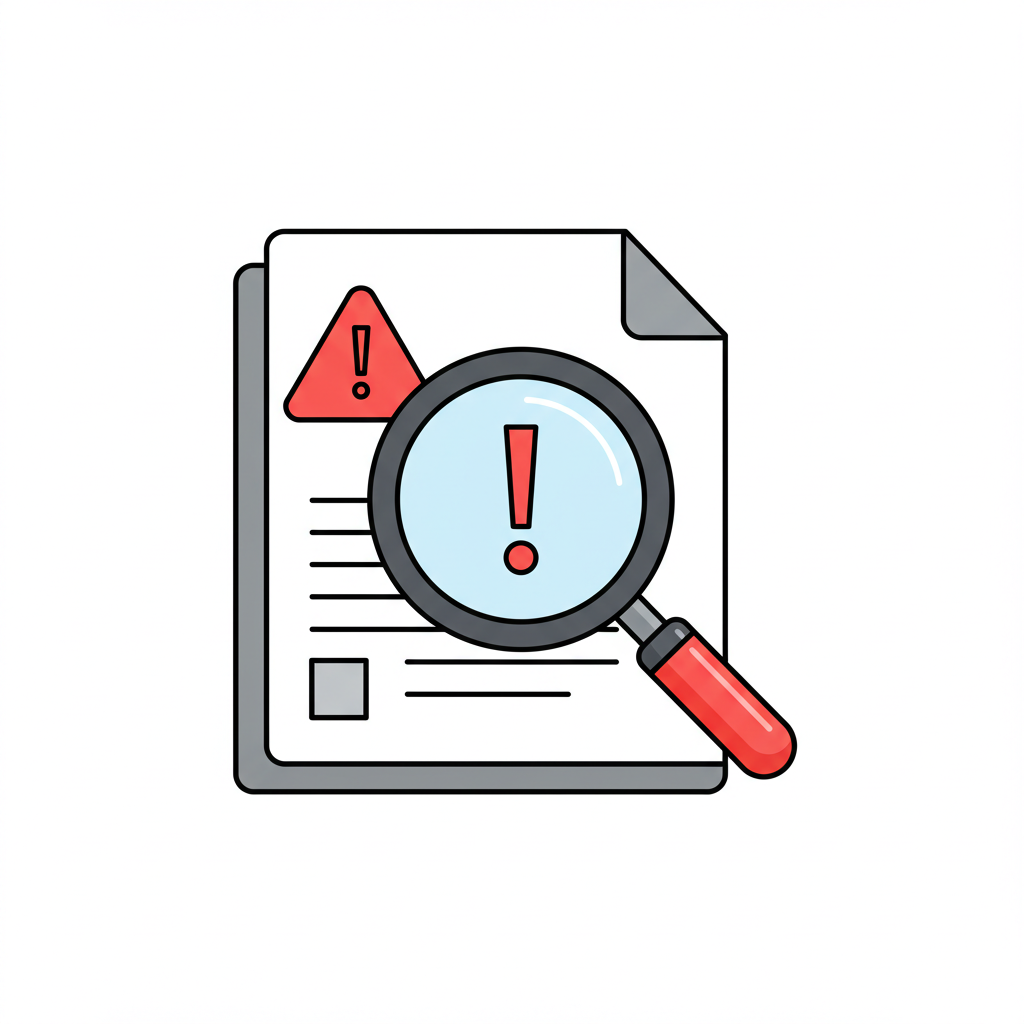
先輩
「最初はリスクポイント抽出法。提出前に『ここがバグや理解のネックになりやすい』と思う箇所を3~5箇所ピックアップして重点的に確認するんだ。」
ユウタ
「なるほど。自分で『ここが危なそう』と意識するだけでも違うんですね。」
先輩
「そう。例えば、複雑な条件分岐や外部ライブラリとのやり取り、テストが漏れやすい箇所などを意識すると、レビューでの指摘の大半を事前に防げるんだ。」
ユウタ
「自分でリスク箇所を整理するだけで、レビューの受け方が変わりそうです。」
先輩
「うん。提出前に危険ポイントを洗い出す習慣をつけると、効率的に品質を上げられるよ。」
② セルフレビュー

先輩
「次はセルフレビュー。提出前に自分のコードを一度読み返して、必ず3箇所改善することを意識してみよう。」
ユウタ
「3箇所だけ…?全部直すんじゃなくて?」
先輩
「全部直そうとすると時間がかかりすぎて続かないんだ。でも3箇所改善するだけでも、コードの完成度は格段に上がる。少しずつ自分で気づく力もつくよ。」
ユウタ
「なるほど。最初から完璧を目指すんじゃなく、改善の習慣をつけるんですね。」
先輩
「そう。その3箇所はロジックのわかりやすさ、変数名の意味、コメントの補足など、自分が読んで気になった点で十分だよ。」
③ 差分確認
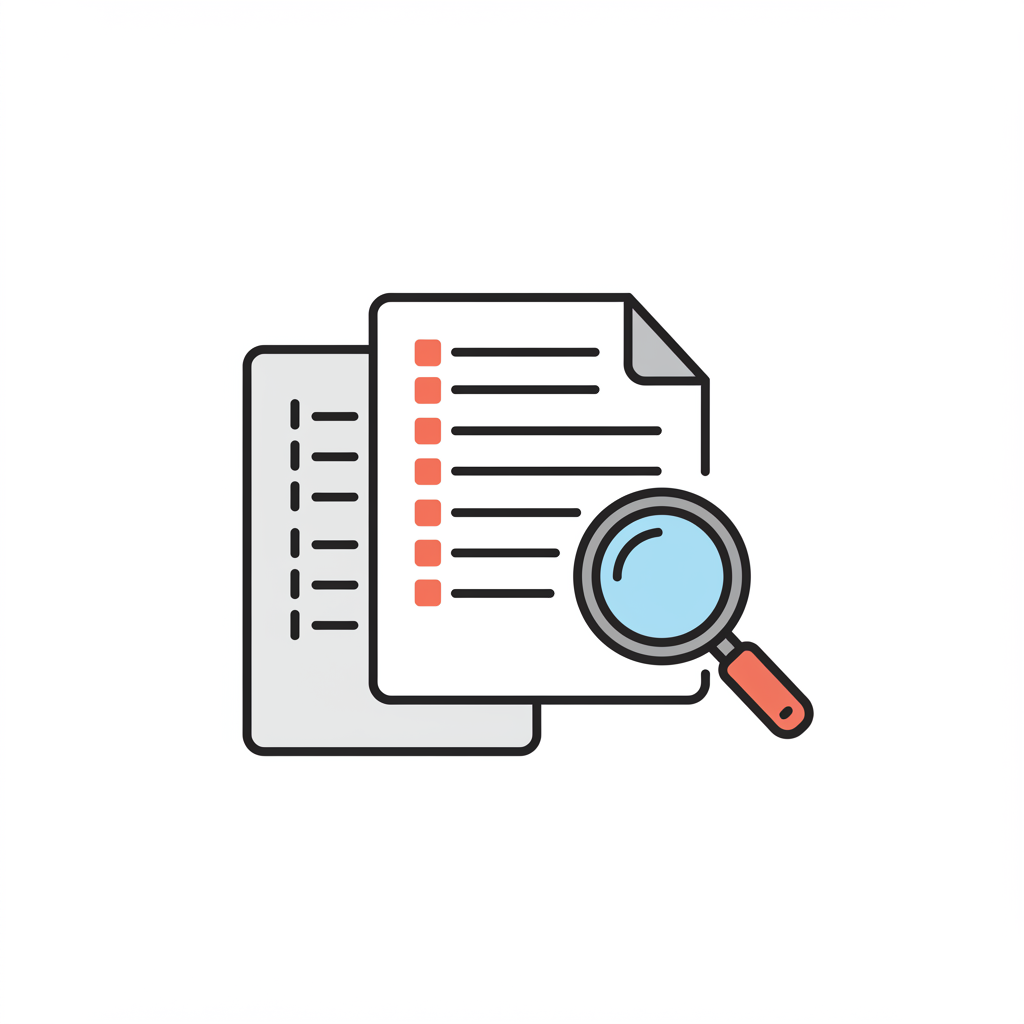
先輩
「最後はPull Requestの差分確認。変更部分だけでなく、全体の整合性も確認するんだ。」
ユウタ
「差分だけじゃダメなんですか?」
先輩
「差分だけだと、他の部分との影響範囲が見えないことがある。関数の呼び出し元や設定ファイルとの整合性をチェックすると、レビューでの追加指摘をぐっと減らせるんだ。」
ユウタ
「なるほど。全体像を意識するだけで、見逃しが減るんですね。」
先輩
「そう。提出前に全体像を把握しておくことも、品質向上の大きなポイントだよ。」
先輩
「この3つのメソッドを習慣にすれば、レビューの細かい指摘は減るし、自分のコードに自信を持って提出できる。焦らず少しずつ取り入れてみよう。」
ユウタ
「わかりました!リスクポイントを意識しながら、改善箇所を見つけて全体を確認する…。今日から早速試してみます!」
📌まとめ(読者へのヒント)
- リスクポイント抽出法:提出前にバグや理解のネックになりそうな箇所を3~5箇所ピックアップして重点確認
- セルフレビュー:提出前に自分で読み返し、必ず3箇所改善する
- 差分確認:変更部分だけでなく全体の整合性も確認する
💡応用のヒント
- チームでチェックポイントの共通リストを共有すると、レビュー基準の統一にもつながる
- 提出前に簡単なテストケースを実行することで、より安全にレビューに出せる
- 次回は「レビューコメントを活かす!指摘を次の成長につなげる方法」をお届け予定
